みなさん、品出しは慣れてきましたか?
品出しは時間が掛かる作業なので、スピードを上げたいと考えている人は多いと思います。
でも、無茶をすれば疲れてしまうばかりか体を壊しかねません。
そこで今回は、品出し経験豊富な管理人が工夫してきたことを、初心者でも分かりやすいように、検品のやり方から品出しの手順を解説しつつ、効率的に作業をするための方法を教えます。
この記事を読めば、「品出しが遅い」「きつい」と悩んでいた方も、作業がぐっと楽になりますよ!
納品

納品は以下の4つの温度帯に分かれています。
- ドライ(常温):菓子、雑貨、ペットボトル飲料など
- 米飯・パン(20℃):おにぎり、弁当、菓子パンなど
- チルド(5℃):サンドイッチ、サラダ、スイーツなど
- フローズン(-20℃):冷凍食品、アイスクリーム、FF食材など
ドライとフローズンの2つは基本的に夜間に入荷するため、品出しを行う時間帯は夜間帯になることが多いです。
ドライはカゴ台車からドライバーが荷物を降ろしてくれる場合と、自分で降ろす場合があります。
自分で降ろす場合は、お店の台車の上に一旦降ろして売り場まで運びます。
フローズンはドライバーが運び入れた大きな保冷容器(フローズンシッパー)から、基本的に商品を自分で取り出す必要があります。
※商品はお店の物なので、ドライバーが触ることでの破損のリスクを最小限に抑える目的があります。
ドライバーが荷物を納品したことを証明するために、レジでのIDカードのスキャンや納品書へのサイン、お店のハンコを押すなどの処理をします。
また、インターネット注文品やクリスマスケーキなどの予約商品の納品、お店の返品商品などがあれば、別で伝票にサインをします。
検品

商品の状態確認や、発注数と納品数が正しいかチェックをします。
お客さんが検品前に商品を取っていくこともあるので、バックヤードで検品するのが望ましいですが、売り場に出して検品をする場合は納品後、速やかに検品に取り掛かります。
ハンドスキャナーで検品用のバーコードを1つずつ通して確認します。
納品数が少ない場合は修正し、多い場合は修正するか、修正はせずに後日ドライバーに返品をします。
納品数が合わなくて修正があった場合は、誤入力で修正したと勘違いされないためにメモなどで伝えておくと親切です。
注意点
検品をしながらの商品の品出しはできるだけ止めましょう。
商品を全て出し終えた後、未検品商品があると画面に表示された場合、バーコードを通さずに品出しをしたのか、それとも本当に未納品なのかが分からなくなります。
すべての商品を検品してから商品を売り場に出すようにしましょう。
また、台風などの悪天候の日には物流が混乱しやすく、納品ミスや商品の破損の確率が高くなるので、いつもよりも慎重に検品をしましょう。
仕分け
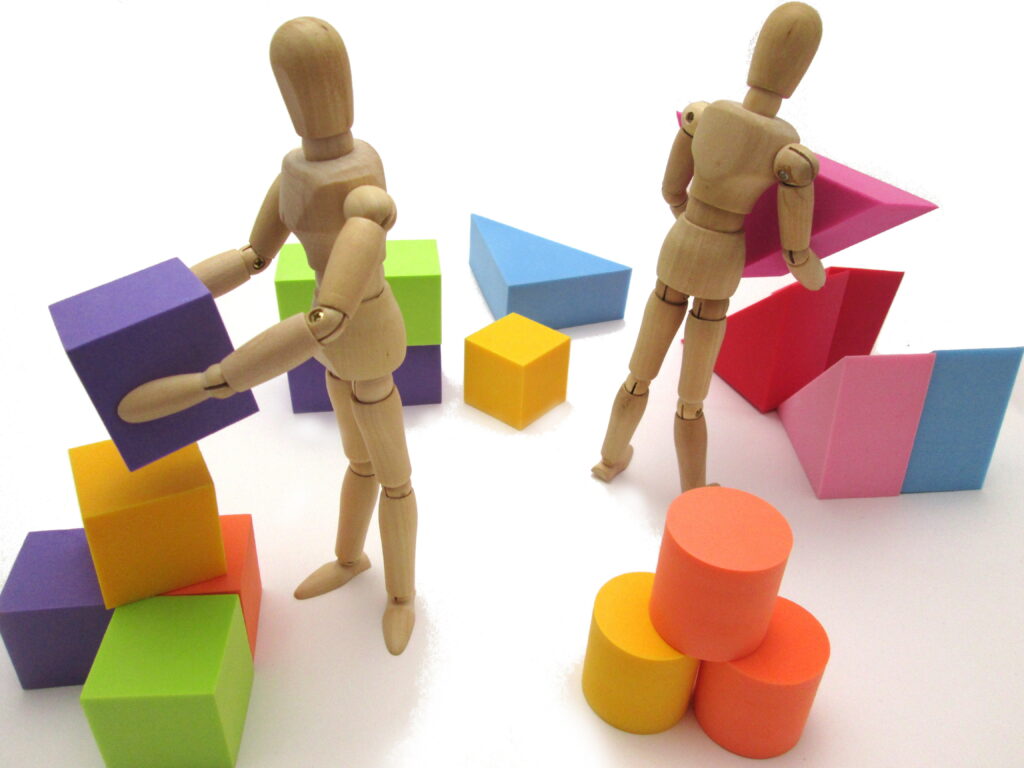
スナック菓子、インスタント食品、栄養ドリンクなど、それぞれ売り場が離れていることが多いと思います。
納品された商品を分類ごとに仕分けて、各売り場の前にまとめて置くことで、品出しの際に無駄な歩行が減るので、時間を短縮することができます。
細かく仕分けると時間が掛かるので、棚2本分をベースに考えると良いでしょう。
日頃からどこに何を置いているかを意識して売り場をチェックすることで、仕分けるスピードは速くなります。
品出し

1.出す順番を決める
客数と、荷物を置く位置からレジまでの距離を意識します。
お客さんがよく来る時間帯はレジから近い荷物を出して、あまり来ない時間帯はレジから遠い荷物を出すようにすると、レジに向かう労力と時間を削減できるので効率が良いです。
来客の波はある程度決まっていると思いますので、大まかに出す順番は決めておきましょう。
2.開封する
梱包資材から商品を取り出します。
段ボールの場合は開けたい部分を内側に押し込むと、テープや接着面が少し浮いて隙間ができるので、開けやすくなります。開かない場合は、中の商品に注意してカッターやハサミでテープに少しだけ切り込みを入れて下さい。
開封時は箱の角や端で指を切ることがあるので、力任せに開けないよう気を付けてください。
また、外箱・外袋に入ったままだとお客さんが1個ずつ購入できないので、ガムなどを陳列している商品の奥に補充する場合でも、外箱・外袋から取り出しましょう。
3.距離を詰める
「商品⇔人」「商品⇔売り場」なるべくこの距離を詰めます。
距離を短くすることで品出しの時間も短くなります。
オリコン(折りたたみコンテナ)に入っている商品は、空きのオリコンがあれば台として使い、腰を曲げなくても商品を取り出せるように腰ほどの高さに調節します。番重(おにぎりなどを運搬する容器)も同様です。
持つことが可能なら腰の位置に当てて持つことで、商品と人との距離を詰めることができます。
軽い商品は売り場に腕を伸ばして容器から商品を取り出すことで、商品と売り場との距離を詰めることができます。
商品棚が高くて手が届きにくい場合は小さい脚立などの台を使います。
商品棚が低い場合は段ボールを敷くことで、膝立ちしながらでも膝の負担を軽減できます。
商品を床から持ち上げる際は腰に負担を掛けないように、膝を軽く曲げて背筋を伸ばしながら胸を張ることを意識して下さい。
4.先入れ先出し
手前から古い期限順になるように、先に仕入れている商品を先に出して商品補充を行います。
陳列されている商品を手前に寄せるか、いったん奥へ押し込むと、補充できる分のスペースが生まれるので、だいたいの補充数が分かります。
期限とパッケージデザインが同じであれば、先入れ先出しを気にせずに補充しても大丈夫です。
また、パッケージデザインが変わっていたり、似たデザインで判別しにくい場合は、JANコードの末尾4〜6桁を確認してください。
数字が一致していれば、同じ商品です。
※カップラーメンなどの2段積みの商品の場合は、古い期限の商品が下にならないように注意して下さい。
※雑貨などの回転率が低い商品は、先入れ先出しをしないとパッケージが日焼けなどで劣化していくので先入れ先出しを実施して下さい。
5.適量を出す
商品を陳列し過ぎていると売り場が乱れて見えるだけではなく、商品が落ちやすくなり、破損や痛みの原因にもなります。
特に棚の横に吊っている商品は、お客さんの肩などに当たりやすいのでよく落ちます。
商品の表面が上を向くほど補充しないのがポイントです。
棚にある商品は前に飛び出ないようにして下さい。
バナナなどの生鮮食品は重なるまで陳列すると傷みやすくなるので注意して下さい。
出し切れなかった商品を保管する時も、整理して適量を保管することで破損などのリスクを防げます。
お店用のオリコンや在庫棚に入り切らない場合は無理をして入れずに箱のまま別の場所に保管しましょう。
適量の品出しは、売場が「綺麗」に見えることにもつながります。
6.片付け
補充が終わった商品の外箱は潰して小さくすることで、ゴミ袋を使う枚数を削減できます。
外箱の底が折り畳まれて作られているものは簡単にバラせますが、底が接着剤で接着されているものは底に隙間がある場合、内側に力を入れることで楽に潰すことができます。
潰しにくいものがある場合はゴミ袋にまとめて入れておいて、足で踏んで上から圧力をかけて潰しても良いと思います。
補充が終わった商品の段ボールは解体して折りたたみ、他の段ボールの口に挿し込んで片付けましょう。
まとめて片付けるよりも、その都度片付けた方が、後で床から段ボールを拾い上げる動作をしなくて済みます。
まとめ
品出しは慣れるまでは大変ですが、手順を覚えていけば、自然とスピードも上がってきます。
今回紹介したポイントを押さえるだけでも、作業の負担はかなり減るはずです。
また、品出し中はお客さんの邪魔にならないように作業しましょう。
初めのうちは焦らなくて大丈夫です。
自分のペースを守りながらやっていきましょう!
新商品の品出し方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
→ 新商品の品出し方法の詳細はこちら

